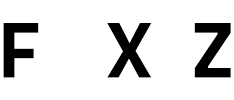不当誘導の防止を目的とした民間認定がスタート
ウェブ上で利用者を誤誘導する「ダークパターン」の排除を目指し、ダークパターン対策協会が新たな企業認定制度を導入した。
この制度では、ダークパターンを使用していない企業に対し、認定マークの表示を許可することで、消費者が信頼できるサイトを一目で識別できる環境を整える。
目次
審査機関に金融機関も参画、全国展開を視野に
認定プロセスは、企業の自己審査に続いて、金融機関や消費者団体による一次審査、最終的な協会の承認という三段階構成。
金融機関が審査に加わることで、融資条件などを通じて倫理的なウェブ運営を促す狙いがある。
地方銀行の参画も予定され、認定制度の全国的な普及を目指す。
被害額は年間3万3000円、企業の責任意識が問われる
協会の試算によると、消費者がダークパターンによって被る被害は年間1人あたり約3万3000円に上る。
こうした被害を減らすためには、企業が透明性を確保し、広告表示や販売ページ設計の見直しを進める必要がある。
制度導入により、企業倫理の可視化と信頼構築が求められている。
通報と教育を通じた社会的啓発活動も展開
協会は「ダークパターン・ホットライン」を開設し、悪質サイトの情報を受け付けている。
通報件数は開始から3か月で60件を超えた。
また、小中高生向けの啓発動画を公開し、判断力を育む教材として学校現場での活用を促している。
欧米規制とのギャップ埋める民間主導の試み
欧米では「欺瞞的デザイン」として法規制の対象となっているが、日本では包括的な法律が存在しない。協会の小川晋平代表理事は「民間の取り組みで信頼の基盤を築くことが重要」と述べた。
今後、NDD認定は企業の社会的信用を左右する指標となりそうだ。