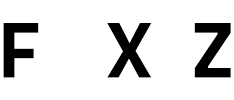抑止力と対処力強化を掲げる新防衛戦略
小泉進次郎防衛相は10月22日の記者会見で、潜水艦の動力として原子力を採用する可能性を排除しない姿勢を示した。「どれかに決め打ちせず、抑止力・対処力を向上させる方策を検討したい」と述べ、日本の防衛政策の柔軟化を印象づけた。新政権下での装備開発方針は、これまでの制約を超えた議論の始まりとなっている。
自民・維新の合意が政策転換を後押し
自民党と日本維新の会は、20日に締結した連立合意書で、長射程ミサイルを搭載できる「次世代の動力」を活用した潜水艦の保有を推進する方針を確認した。加えて、防衛装備品輸出を「救難」などの非戦闘目的に限ってきた5類型制度を2026年に撤廃する内容も盛り込まれた。こうした合意により、政府は従来の防衛政策の枠組みを見直す動きを加速させている。
装備輸出の見直しで産業基盤を再構築
小泉氏は防衛省での訓示でも、輸出制度の再構築に言及した。これまで攻撃用兵器の輸出は実質的に封じられてきたが、小泉氏は「日本にとって望ましい安全保障環境を創出するための重要な政策的手段」と位置づけ、持続的な防衛産業の確立を強調した。国内産業の国際競争力を高め、装備品の共同開発や海外市場への進出を視野に入れた政策が求められている。
安保3文書の前倒し改定へ省内調整進む
防衛相はまた、2022年末に策定された国家安全保障戦略など3文書の改定に前向きな姿勢を示した。高市早苗首相が改定を指示したことを受け、「真に実効的な防衛力を構築するため、全力で取り組む所存」と語った。装備開発、戦略立案、予算配分の各面で見直し作業が進む見通しであり、政策の一体化を図る狙いがある。
外交・経済体制も一新へ
新政権では防衛と経済外交の連携体制も刷新されつつある。茂木敏充外相が米国との調整を担当し、赤沢亮正経済産業相や城内実経済財政相と連携して日米経済交渉を推進する計画だ。前政権で交渉を一任されていた赤沢氏の役割が分担化され、複数閣僚による協調体制が取られる。安全保障と経済の両面で、政府全体の政策運営に変化が見られる。