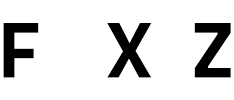51年続いた暫定税率廃止が合意された経緯
ガソリン税の暫定税率は長年にわたり国民負担の象徴とされてきた。昨年12月には自民、公明、国民民主の3党が廃止で合意したものの、今年2月に協議は行き詰まった。しかし、与党が参院選で過半数を割ったことで、情勢は一変。与野党は年内に廃止を実現する方向で足並みを揃えつつある。
自治体から広がる税収減への懸念
暫定税率撤廃による影響は大きく、国と地方の歳入は約1兆円減り、軽油引取税を含めると1.5兆円規模に達する見込みだ。地方の収入源が削がれることへの不安は根強く、「生活基盤となるサービスやインフラ整備に支障が出る」との指摘が各地から上がっている。こうした懸念を背景に、国会では代替財源の確立が最大の争点となっている。
野党は「民意」を根拠に速やかな実施を要求
野党側は財源論を抑えてでも減税を優先すべきだと主張している。玉木雄一郎代表は「51年間続いた暫定税率を廃止するのは民意だ」と強調し、すでに補助金や税収の増加で問題は解決済みだと訴えている。与党の慎重姿勢をけん制する発言は、支持層に向けたメッセージとも映る。
与党は「持続可能な制度設計」を主張
一方で与党は、拙速な廃止は将来の財政運営に支障を及ぼすと警戒を強めている。宮沢洋一税調会長は「恒久財源の裏付けがなければ無責任だ」と発言し、野党側に代替策の提示を求めた。政権としては、国民への還元を否定しないものの、持続可能な仕組みを整える必要性を訴えている。
秋の臨時国会で決着の見通し
野党は8月の臨時国会に「11月1日からの廃止法案」を提出しており、秋の国会審議で成立を目指す。国民の生活支援と財政健全化という二つの課題をどう調和させるのか、与野党の調整は最終局面を迎える。結果次第で、日本の税制とエネルギー政策の方向性が大きく左右されることになる。