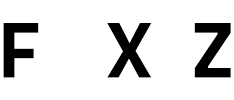増産方針転換の背景
政府はコメの需給不足と価格高騰を受け、増産重視の方針へ移行した。石破首相は関係閣僚会議で、備蓄米放出の遅れや需要予測の誤りを認め、耕作放棄地の活用と輸出拡大、スマート農業導入を推進する考えを示した。中山間地域の棚田保全も視野に入れ、水田政策の見直しを行う方針だ。
農業現場の慎重な反応
現場の農家からは「生産力の低下や人手不足で増産は容易ではない」との声が多い。新潟県の農家は異常気象や長年の減反政策で生産基盤が弱まり、急な増産は難しいと指摘。価格下落による収入減も懸念されており、安定的に生産を続けるための所得補償を求めている。
農業団体と知事会の提言
JA秋田中央会は、昨年の価格高騰の原因として政府の需給予測の甘さを挙げ、今後は正確な見通しを示す必要があると主張。また、休耕田を再び水田に戻すには高額な費用と長い時間がかかるため、国や自治体の支援が不可欠とする。全国知事会長の宮城県・村井知事は「価格が不安定になれば意欲が低下する」と述べ、山形県・吉村知事も長期的な農業環境整備の重要性を指摘した。
政策と党内調整の動き
農林水産省は生産者支援やスマート農業導入を盛り込んだ予算案を提示したが、自民党農林関係役員会は了承を見送り、再調整を求めた。立憲民主党も増産には賛成しつつ、具体的な実現策や見通しを質す構えを見せている。党派を超えた議論の必要性が高まっている。
増産実現への条件
増産政策を成功させるには、生産現場の課題解決と需給予測の精度向上が不可欠だ。農家が安心して生産を拡大できる環境整備、価格変動を抑える制度的枠組み、人材確保策の実施が急務となっている。政府は地域の実情に即した支援策を講じる必要がある。