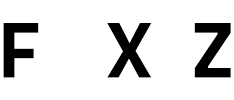想定外の好漁が生んだ過剰水揚げ
例年不漁が続いていたスルメイカが、今年は予想を大きく上回る水揚げを記録している。中でも小型漁船によるイカ釣りが突出して好調で、全国の漁獲量は10月中旬時点で5,300トンを突破。割り当てられた枠の上限を超えたことから、水産庁は月末までに漁の停止命令を出す準備を進めている。
枠上限を繰り返し拡大も限界
水産庁は今期の漁期開始時に、小型漁船への漁獲枠を2,800トンに設定していた。しかし豊漁を受け、秋にかけて4,900トンへ引き上げた。それでも勢いは衰えず、短期間で上限を突破。記録的な水揚げが続いた結果、枠管理の見直しが追いつかないまま制度上の限界に達した。漁獲可能量制度が導入された1990年代以降、スルメイカで停止命令が出るのは初となる。
管理措置がもたらす地域への影響
今回の命令は、主に北海道や東北地方の沿岸を拠点とする小型漁船に影響を及ぼすとみられる。漁期は来年3月まで続くが、命令が発出されれば漁を再開できない期間が生じる。地元漁協では「漁が好調なのに船を出せないのは痛手」との声もある。一方で、資源保全を重視する立場からは「今後に向けた警鐘」として評価する意見もある。
他漁業への波及防止と再配分の検討
水産庁は小型漁船以外の漁業については停止の必要はないとしており、沖合底引き網や中型船以上のまき網漁などは操業を継続する予定だ。さらに、漁法間で共有する猶予枠5,700トンを他の漁種から振り替える案も検討しており、影響緩和に向けた調整が進む。こうした運用は、今後の漁業管理の柔軟性を測る試金石となりそうだ。
資源保全と経済の両立を問う局面
記録的な豊漁と厳格な制限措置という対照的な現実は、漁業資源の持続的利用と地域経済の両立という課題を浮き彫りにしている。今後の漁獲枠設定や分配の見直しは、制度の信頼性と漁業者の生活の双方に直結する問題となる。豊漁を喜べない現場の複雑な状況が、資源管理の難しさを象徴している。