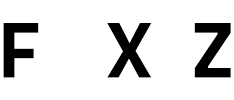実用化の鍵を握るコスト構造に変化
水産研究・教育機構とヤンマーホールディングスが共同で開発した新型水槽により、完全養殖ウナギの生産コストが大幅に引き下げられた。これまで経済的に困難とされていた人工稚魚の生産が、1尾あたり1800円で可能になったことは、養殖技術の実用化に大きな影響を与えるとみられている。
繊維強化素材の導入と形状工夫の効果
開発された水槽には、安価で加工性に優れた繊維強化プラスチックが使われており、形状は幼体の成長に配慮した設計となっている。特に、稚魚の移動作業や成長ステージにおける管理がしやすい構造となっており、これが効率化とコスト削減の決め手となった。
大量育成によるスケールメリットが発揮
1台あたり1000尾という育成実績は、商用展開への大きな指標となる。従来は少数単位での育成が中心だったが、この新技術によって一気に量産が現実味を帯びてきた。また、給餌や環境制御における技術も進化し、生存率の向上が確認されている。
完全養殖の市場展開に向けた課題と展望
これまでウナギの完全養殖は「技術的に可能でも、経済的に不可能」とされてきた。だが今回のブレイクスルーにより、商業化への障壁が大きく取り除かれた。今後の焦点は、量産体制の拡充と消費市場での価格競争力の確保に移ると見られる。
国際的規制と国内消費構造が影響を与える背景
EUはワシントン条約への掲載を通じ、ウナギの国際取引規制を強化する構えを見せている。日本では、食用ウナギの大半が輸入に頼っており、国際価格の変動リスクが大きい。そのため、政府は自国での安定供給を目指し、完全養殖の推進を国家戦略の一環として位置付けている。