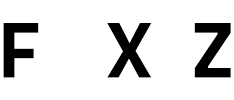京都発のAI診断ソフトに厚労省が医療機器認可
国際電気通信基礎技術研究所(ATR)とその研究機関は、うつ病の診断支援を目的としたAI解析ソフトを開発し、厚生労働省から薬事承認を取得した。ソフトは、fMRI画像から脳活動を分析し、うつ病の兆候を数値で表示する仕組み。これは日本初の取り組みであり、客観的診断の礎となる可能性がある。
目次
精神疾患特有の診断困難に対応する狙い
うつ病は、感情の落ち込みや不眠など症状が多様で曖昧であり、診断は医師の経験や主観に大きく左右される。さらに、他の精神疾患との鑑別が難しく、誤診のリスクも高い。今回のAIソフトは、こうした課題に対して脳活動という客観的指標を導入することで、診断の一助となることを目的としている。
長期的データ収集で学習精度を高めたAIモデル
研究チームは10年に及ぶ長期調査を通じて、合計2975人分の脳画像を蓄積。fMRIを用いて収集されたデータをAIに学習させ、うつ病患者に特有の脳回路パターンを抽出。結果として、およそ7割の判定精度を実現したと報告されている。これは、AIによる精神疾患分類としては高い水準にある。
通常検査に組み込み可能な運用の柔軟性
本ソフトは、通常のMRI検査にfMRI撮影を追加する方式を採用。撮影時間はわずか10分程度で、検査全体のフローに大きな影響を与えず運用可能。この手軽さにより、医療現場への導入も現実的で、精神医療におけるAIの実用化が一歩進んだことになる。
診断の客観性を高める補助的役割としてのAI技術
AIによる診断は、あくまでも医師の補助的手段として位置づけられている。しかし、診断精度の向上や偏りの是正においては大きな意義を持つ。今後、他の精神疾患にも応用可能なアルゴリズム開発や臨床試験が進むことが期待される。